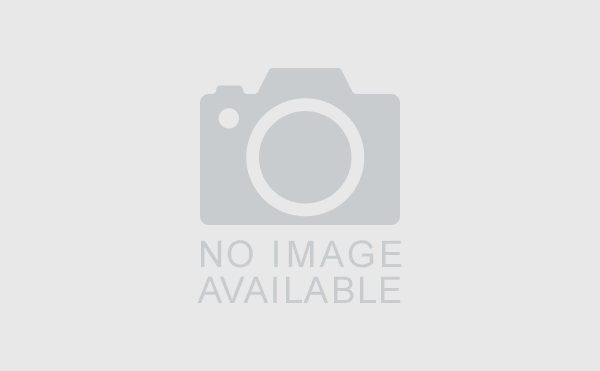鹿児島県警による「情報源暴き」に抗議する
福岡県を拠点とするウェブニュースサイト「ハンター」の運営者が、鹿児島県警の情報漏洩を巡る地方公務員法違反事件の関係先として4月8日に同県警の家宅捜索を受け、パソコンに保存していたデータが消去されたとして、同県警に苦情を申し出ました。押収されたパソコンに捜索令状に示された内容とは別件の警察内部からの提供資料があったとされ、その資料を組織外に流出させたとして鹿児島県警の前生活安全部長が5月31日、国家公務員法違反容疑で同県警に逮捕されています。公務員による情報漏洩に関連して警察がメディアを家宅捜索し、押収した資料を基に情報源を逮捕する―。情報提供者のメディアへの信頼を守り、正確な情報に基づく市民の「知る権利」と報道の自由を確保するために必要な記者の職業倫理として「情報源の秘匿」が重要視されてきた民主主義社会では許されない権力の暴走です。メディアを捜査対象とした鹿児島県警と、捜索を許可して捜査権の濫用にお墨付きを与えた裁判官に強く抗議します。
逮捕された前部長は6月5日、鹿児島簡裁での勾留理由開示手続きで、組織ぐるみの不祥事隠ぺいを県警本部長が主導した、と主張しました。警察不祥事に関する取材を長年続けていることで知られ、家宅捜索を受けた「ハンター」への寄稿も行っている札幌市在住のライターに内部資料を郵送したことも、前部長は弁護人を通じて明らかにしています。前部長は簡裁の法廷で「県警本部長が県警職員の犯罪行為を隠蔽しようとしたことが許せなかった」「書類を送れば積極的に取材してくれると考えた」と述べていることから、隠された組織内部の腐敗を告発しようとする公益通報の意図は明確です。不祥事を明るみに出すメディアへの信頼もうかがえます。情報提供を理由にした内部告発者の逮捕は、善意の通報者に身の危険を感じさせ、大きな委縮効果を生みます。そればかりか、メディアを捜査対象とすることで、「権力の腐敗に切り込む調査報道は危険だからやめておこう」という報道側の悪しき自主規制につながりかねません。
新聞労連や労働団体、法曹界、多くの市民が反対する中で1999年に成立した盗聴法(通信傍受法)の国会審議では、後に検事総長となる松尾邦弘・法務省刑事局長が「報道の自由あるいは取材源の秘匿の問題というのは、私どもは大変重要なことだというふうに理解しております」と述べた上で、「報道機関が取材の過程で行っている通信につきましては、基本的には通信傍受の対象としない」と明言しています。常に存在する権力による「情報源暴き」の懸念に対し、捜査機関は抑制的な姿勢を取っています。今回の鹿児島県警の対応は、従来の対応を大きく逸脱するものです。
警察の不祥事は、全国各地で長年相次いでおり、組織の閉鎖性もあって、その多くが自ら公表されていません。大阪府警の警察官が落とし物として届けられた拾得金を横領しただけでなく、届け出た主婦を犯人扱いした問題や、北海道警の裏金問題は新聞報道で明るみになり、それぞれ88年に読売新聞大阪本社が、2004年に北海道新聞社が新聞協会賞を受賞しています。とりわけ道警裏金報道は、全国の警察組織に同様の問題があることを各社が報じる発端になりました。いずれも、報道が警察組織の歪みを指摘した一例です。
新聞労連は4月26日、兵庫県の斎藤元彦知事を批判する文書を作って関係機関に配布したとして同県幹部職員が解任された問題で、神戸新聞記者に対して文書を受け取ったかどうか「聴取」し、回答を求めた兵庫県当局に対して抗議声明を発表しています。その声明でも引用した新聞労連の「新聞人の良心宣言」(1997年)は、公的機関や大資本などの権力を監視し、その圧力から独立するために「情報源の秘匿を約束した場合はその義務を負う」「取材活動によって収集した情報を権力のために提供しない」と規定しています。報道に携わる私たちは、市民の「知る権利」と報道の自由を脅かす警察権力の暴挙に連帯して対抗する必要があります。
以上
2024年6月19日 日本新聞労働組合連合(新聞労連) 中央執行委員長 石川昌義