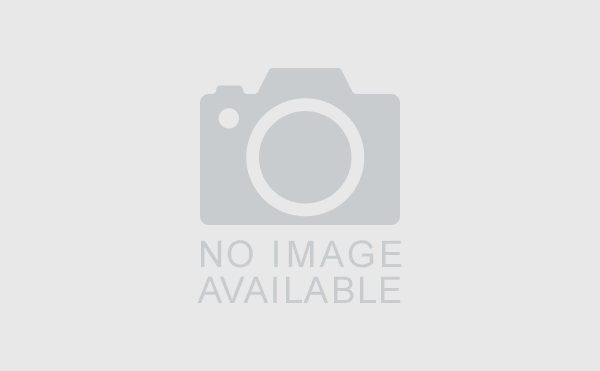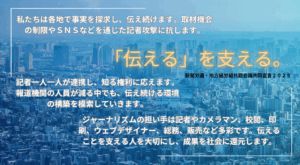ジェンダー平等宣言2025 (vol.1.0)
新聞労連ジェンダー研究部
長年、典型的な「男性社会」にあった新聞業界。旧態依然とした働き方や価値観の下で、まるで“組織のコマ”のように社員が扱われる―そんな状況から少しでも早く脱却するため、新聞労連ではジェンダー平等宣言をまとめました。
働きづらさは、女性のキャリア形成や、男女問わぬハラスメント被害にもつながっています。その根底には「家事や育児は女性がやって当然」というケアワークへの無理解を前提に、長時間労働を強いたり、個人の人権を無視したりする、社業優先の考え方がありました。
報道機関の一員として、現在働く私たち、これから門戸をたたく学生たちのためにも、今ジェンダー平等を推し進めなければ、業界の存亡にも関わります。
失ったものは取り戻せずとも、よりよい明日にするため。一人一人の尊厳が守られた職場環境で、やりがいを感じながら仕事を全うするため――。
今ここに宣言します。
1)多様な暮らしを守るために
育児や介護などのケアワーク、業務中の事故や突然の心身の病気は、誰しも直面する可能性があります。そのような時期であっても、多様な仕事のあり方を模索・確立することができる職場を目指します。労働時間も柔軟に配慮しながら、自分と自分の家族を大切にして、健康で豊かな人生を送れる職場を、労使で模索します。そのために、仕事の属人化や長時間労働を解消し、マイノリティーの意見も尊重され、ジェンダーフリーで多様な暮らしが守られるしなやかな組織作りを目指します。
2)男性偏重でない組織づくりに
男性偏重の同質性がメディアにはびこることが、働き方の硬直化を招き、ハラスメントの温床にもなっています。多様な意見が反映されない報道にもつながってしまうため、ジェンダーギャップの解消は喫緊の課題です。まずは意思決定層に女性の比率を増やし、女性の意思も反映されるような会社組織を目指します。新聞労連などはかねてより女性管理職比率3割という数値目標を掲げてきました。ただ、この実現を目指すことと並行して、「女性管理職比率ありき」で個人の暮らしや職務経験に合っていない役職に就かされ無理が生じる配置にならないよう、1)で掲げる職場を目指します。会社だけでなく単組の組織も例に漏れず、これまで以上に組合活動の間口を広めるよう努め、オンラインを積極的に活用するなど、ケアワークがあっても参加しやすい組合活動を目指します。
3)ハラスメントと、ハラスメントにつながるものの根絶
あらゆるハラスメントは、既に新聞業界で起きています。個人の尊厳を踏みにじるハラスメントは決して許されない行為ですが、報道機関ではハラスメントで苦しむ人たちが絶えません。我々は、こうした状況を断固として許しません。事案を認定して対処するだけでなく、「オールド・ボーイズ・クラブ」とも呼ばれる男性中心の閉鎖的な組織運営や、性別に起因する無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)など、ハラスメントにつながるものをなくしていく努力をします。
※3)のハラスメントの定義は、ILO第190号条約(仕事の世界における暴力およびハラスメント:単発か繰り返されるかにかかわらず、身体的、精神的、性的若しくは経済的損害を目的 とした、もしくはこれらの損害を引き起こすもしくは引き起こす可能性がある一定の範囲の許容できない行為及び慣行又はその脅威をいい、 ジェンダーに基づく暴力及びハラスメントを含む)に基づく。
4)点検・検証の仕組みの検討
上記1~3について、アップデートすべき要素はないか常に点検し、到達度や実施状況を定期的に検証できるよう、仕組みを検討します。
以上